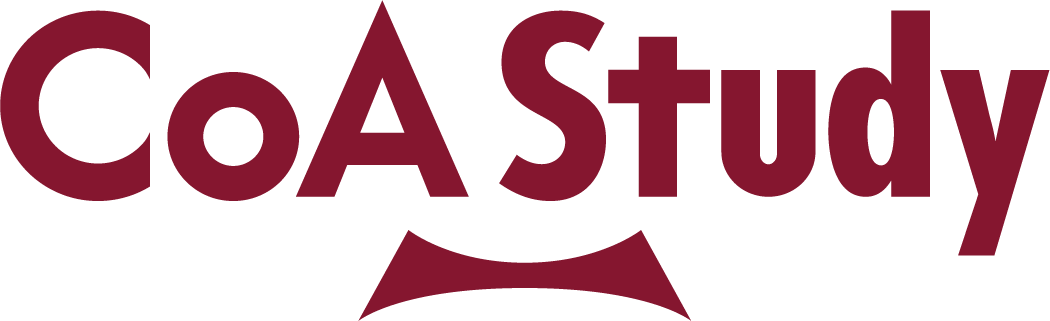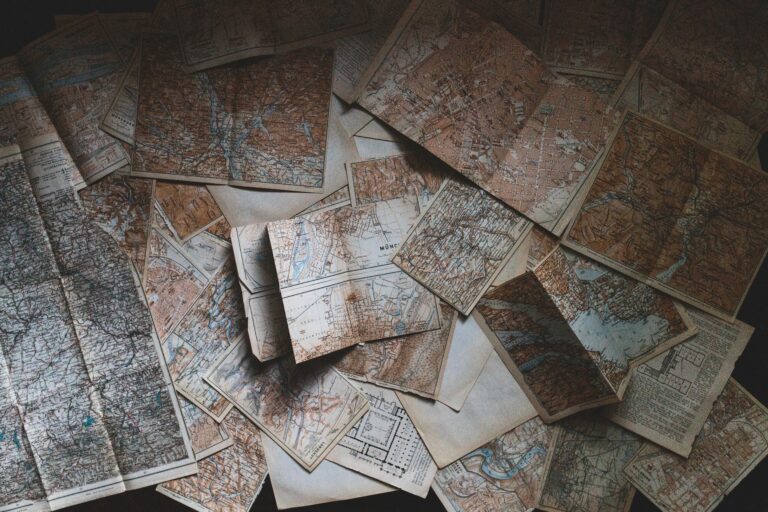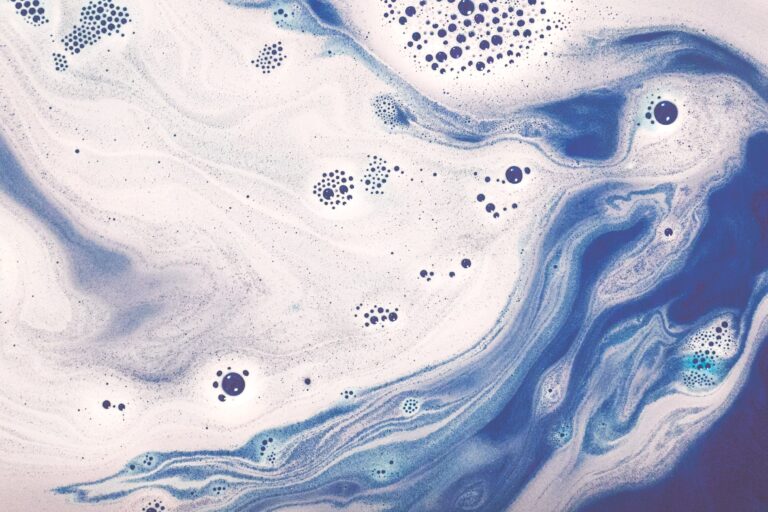研究者や技術者のキャリアは、深い専門性に支えられている一方、その価値がどこで最も発揮されるのかを本人が正確に把握するのは簡単ではありません。大学や研究所、あるいは特定の企業環境に身を置いていると、自分のスキルがどれほど市場で希少なのかに気づかないまま働き続けてしまうことは珍しくないでしょう。
しかし近年、産業界ではDeep Tech*をはじめとする高度な専門領域をバックグラウンドとした先端事業が次々に立ち上がり、研究で培った技術がそのまま新しいキャリア機会につながるケースが増えています。
今回は、 大学から産業界へ大きく舵を切り、550万円から1000万円へ年収が跳ね上がったMさんと、 地方メーカーから大手メーカーへ移り、550万円から720万円へキャリアアップしたFさんの、 “気づかれなかった専門性が評価された瞬間”を追った転職ストーリーをご紹介します。
Deep Tech は、既存技術の延長ではなく、科学・工学の最先端研究に基づく高度な技術革新を指す言葉です。AI、量子、ロボティクス、バイオテック、材料科学、エネルギー工学など、専門的な知識と長期的な研究開発を必要とする領域が中心で、産業構造や社会基盤そのものを変える可能性を持つ技術を総称して用いられます。
アカデミアの研究力が、事業成長の源泉に──流体工学の新しい需要
高度な専門知識を持つ研究者であっても、そのスキルがどこで最も求められているのかを自覚しないまま日々を過ごしてしまうことがあります。研究室では当たり前のように扱っていた技術が、産業界ではほとんどの企業が喉から手が出るほど求めている“希少資源”であることに気づかないままです。実は、近年の採用市場では、まさにこうした“気づかれない専門性”こそが大きな価値を生み出しています。
流体工学はその代表例です。熱流体や多相流、あるいは空気や流体の微細な挙動を読み解く研究は、大学の研究室では“当たり前”の営みでも、産業界では専門家がほとんど存在しない領域です。高度なCFD*解析を扱える人材や、現象と数値解析の両方を深く理解できる技術者はさらに限られています。こうした背景のなかで、航空宇宙領域の技術を基盤としたスタートアップや、CFDとAIを統合させようとする先進的な企業は、流体の専門性を持つ人材を強く求めるようになりました。
*計算流体力学(CFD: Computational Fluid Dynamics)
実際に、流体シミュレーションを専門として大学で研究に従事していたMさんは、当時の年収が550万円ほどでした。研究室では、熱流動や多相流の挙動を理解し、それを数値解析へ落とし込むことは日常の業務であり、特別視することもありませんでした。しかし、彼が次に選んだ転職先は、CFDとAIを統合した新しい解析技術の開発に挑む最先端スタートアップ。そこでは、まさにMさんが積み上げてきた専門性が“事業の核となる能力”として捉えられました。
選考の過程で、大学で磨いてきた現象理解の深さや多相流解析の経験が、企業にとって極めて希少で代替の利かないスキルであることが明らかになり、提示された年収は一気に1000万円へと跳ね上がりました。研究室では「普通の技術」だったものが、評価される環境に移るだけでここまで価値が変わるという事実は、現代の技術者市場を象徴しています。
地方の現場経験が大手で覚醒──材料知識と解析力の希少価値
製造業の技術領域では、同じスキルであっても「どこで働くか」によって評価のされ方が大きく変わるケースがあります。特に地方メーカーでは、材料評価から構造解析、製品の性能検証まで幅広く経験を積んできた技術者であっても、その価値が外部から可視化される機会はほとんどなく、希少性が見逃されてしまうことが少なくありません。しかし、大手メーカーに視点を移すと、そうした深い業務経験を持つ人材こそが不足しており、まさに“代替のきかない技術者”として強く求められているのが現実です。
例えば、材料開発の経験や知識をもとにFEM*構造解析を実務レベルで扱える人材は、単に解析に強みを持つだけの人材では到達しにくい、一段高いレベルでの分析や解析結果を提供することができます。地方メーカーでは「担当していたから自然と身についた」と思われがちな経験であっても、大手企業から見れば、それこそが事業の中核を支える重要な専門性となるのです。
*FEM:有限要素法(Finite Element Method)
実際に、地方メーカーで年収500万円台で働いていた技術者のFさんは、大手メーカーの解析・評価部門へ移ることで、年収が700万円台へと大きく伸びました。Fさん自身、「材料の癖を理解しながら解析するのは当たり前」という感覚があり、この待遇は驚きだったそうです。こうしたケースは決して特殊ではなく、複数の専門領域を掛け合わせて理解できる技術者が、現代の製造業でいかに重宝されているかを端的に示しています。
本人が気づかない希少性
興味深いのは、こうした価値の高さに当の本人が気づいていないケースが非常に多いという点です。大学の研究室では流体解析の技術者が周囲にいるため、自分の専門性が特別であるとは感じにくいのです。地方メーカーでは、多能工的に業務をこなす環境に身を置くことで、材料も解析もできることを“普通のこと”だと捉えてしまいがちです。しかし、企業側から見れば、いずれも代替の効かない希少な人材です。専門性そのものが価値なのではなく、「どこで必要とされているか」を知ることによって価値が初めて可視化されます。
また、専門性を深めた先に産業界の先端技術と接続できる瞬間が訪れると、市場価値が大きく跳ね上がるというのも、この二つのケースに共通しています。個別に切り取られがちな領域を行き来できる人材は、研究開発業でも製造業でも常に不足しています。深い専門性を持ちながら、隣接する領域へと橋をかけられる研究開発人材こそ、今の産業界で強く求められている存在なのです。
CoA Study編集部より
今回ご紹介した2つのケースは、稀有な専門性が評価される環境に移ることで、キャリアも年収も大きく変わることを示す象徴的な事例でした。しかし、キャリアの価値は決して年収だけではありません。今後は、「自分のやりたい研究に近づけた転職」 や、「アカデミアポジションへの採用支援」 といった、研究者が専門性を活かして進んでいく多様なキャリアパスについてもご紹介していく予定です。研究者や技術者のみなさまが、自分らしい道を選べるきっかけとなれば幸いです。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。