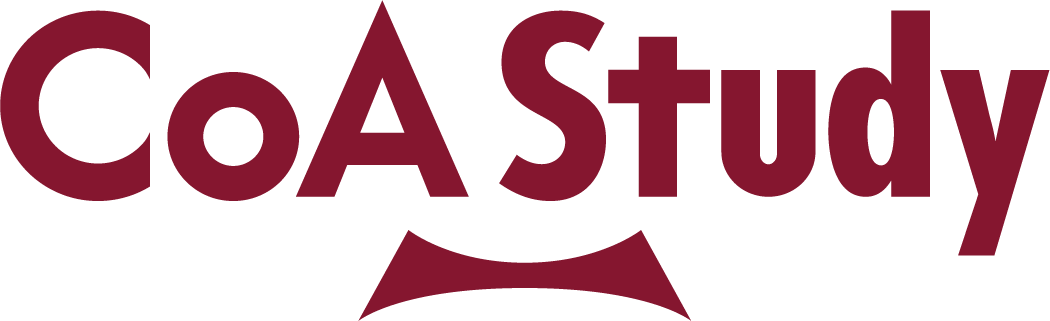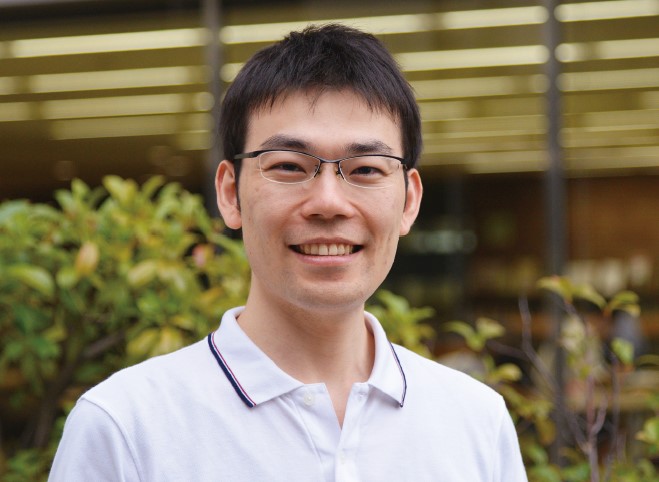異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。
若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。
記念すべき第1回では、電子デバイスおよび集積回路工学の第一人者であり、東京工業大学(現東京科学大)の前学長で、同大名誉教授の益 一哉(ます かずや)先生にインタビューしました。
長年にわたり日本の研究力の強化と次世代人材の育成を牽引してこられた益先生に、日本の研究環境や研究者のキャリアについて伺いました。
任期制が活きるのは人材流動性の高い社会
— 当社では研究開発者の方々の人材流動性を向上し、「研究開発者の可能性を最大化させる」ことを目指して活動させていただいているのですが、益先生は「研究人材の流動性」についてどのような課題があるとお考えでしょうか?
日本の人事制度の設計には大きな課題があると感じています。
本来、日本が研究者に任期制を導入した際には、その背景や目的を十分に理解したうえで取り入れるべきでした。しかし実際には、「任期がある」という表面的な部分だけを、欧米、特にアメリカから模倣してしまったように思います。
アメリカでは博士号取得が研究者としての出発点で、ポスドクや助教を経て7年ほどのテニュアトラック審査を通過すれば、准教授となり終身在職権(テニュア)が与えられます。この制度が成り立つのは、アメリカの退職金や年金制度を含めた雇用文化が背景にあるからです。企業では数年ごとに転職しなければ給与や地位が上がらないのが一般的で、転職しても給与が下がる場合や、事業部の解散・解雇のリスクも高い環境です。その中で、大学は給与こそ企業より低いものの、テニュアを得れば長く安定して勤められる職場として機能してきました。それでも、成果が上がらなければ、退職させられることはないにせよ、給与が上がらないことは企業と同様です。
一方、日本では企業も大学も長く終身雇用が基本でした。ただし、企業に入れば安定して昇給し、大学も同様に長期的に働ける環境が整っていたため、「企業に入った方が安定している」という構図ができ、大学に挑戦的なキャリアを求める動機が弱まってしまったのです。
挑戦的なキャリアを求める動機が高く、企業や研究機関間で人材が自然に移動し、転職が一般化している社会であれば、優秀な人材循環が期待できます。一方、日本のように社会全体の流動性が低い中で、安定した企業には手を付けず、アカデミアだけに任期制を導入しても、期待する優秀な人材循環は起こらないばかりか、若手研究者の将来不安を増幅させる結果になってしまいます。
人材の可能性を最大化するジョブ型雇用とは
— どういった仕組みがあれば、この問題は解決するでしょうか。
近年、日本でも人材の流動性を高める手段として「ジョブ型雇用」という言葉が使われるようになりましたが、その意味は海外本来のものとは大きく異なります。海外のジョブ型は「同じ職務を続けても給与は上がらず、異なる職務に挑戦して初めて昇給する」という仕組みです。しかし日本では、「ジョブ型雇用」という名称だけを取り上げ、給与体系や昇進ルールがほとんど変わらない中途半端な運用が多く見られます。
本来のジョブ型を実現するには、制度設計から抜本的に変える必要があります。社会全体が変わらないまま大学だけに任期制を導入しても、構造的な問題は解決しません。
日本全体、特に産業界は、人材の流動性を高める仕組みをもっと意識すべきです。重要なのは「転職したら給料が上がる」という発想ではなく、職務(ジョブ)そのものに給与を紐づけることです。にもかかわらず、現在の日本では「外部から来た人は前職での経験がなければ給与を上げられない」という考え方が根強く、人材流動化を阻んでいます。
本来、ポジションが人を成長させることも多く、適任と判断すれば任せてみるべきです。うまくいかなければ交代すればよいだけで、初めから門戸を閉ざすべきではありません。固定的な人事制度では、挑戦や変革が阻まれ、日本の組織は競争力を失ってしまいます。柔軟で挑戦を許容する制度設計こそ、人材の可能性を最大化し、産業界全体の活力を高める鍵となります。
科学技術の進歩を次世代にどう伝えるか
— 制度的な課題の他に、研究開発に興味を持つ人材が減ってきているという課題もあるかと思います。
人材の活躍を広げる制度改革は、未来を担う世代の育成にも直結します。その次世代に科学技術の魅力をいかに伝えるかは、極めて重要な課題です。
私が育った1960〜70年代は、日本が高度経済成長の真っただ中にありました。東京オリンピックの開催、新幹線の開通、アポロ計画による月面着陸、大阪万博の開催、そしてコンピューターの登場と、日々新しい技術が生まれていました。
家庭でも、白黒テレビがカラーテレビに、手絞り洗濯機が脱水機付きに、氷で冷やす冷蔵庫が電気式にと、家電製品が次々と進化しました。こうした変化は子どもにもわかりやすく、「科学技術は世界を良くするものだ」という感覚が自然に身についていきました。
現代では家電の進化は当時ほど劇的ではありませんが、ソフトウェア、とりわけAI分野では日々進歩が続いています。この「目に見えにくい進歩」を、いかに子どもや若い世代に実感させ、興味を持たせるかが、これからの大きな課題です。

政府と産業界が一体となる半導体強化策
— 科学の魅力を伝える上で、どのような活動をしていくのが良いでしょうか。
次世代に科学技術の魅力を伝えるには、単なる教育や啓発だけでなく、社会全体が未来技術への投資と挑戦を実行していく姿を示すことが欠かせません。
現在、日本政府は半導体、AI、量子コンピューターといった次世代技術に大規模投資を行っています。量子コンピューターはまだ実用化が不透明な技術ですが、もし実現すれば現在の暗号を瞬時に解読し、従来なら何万年もかかる計算を一瞬で処理できる可能性があります。そのため各国は、実現した場合のセキュリティや社会インフラへの影響に備えて研究を加速させています。
TSMCの誘致やラピダスの設立には数兆円規模の資金が投じられ、量子分野にも数千億円規模の予算が議論されています。これは過去30年では見られなかった規模であり、日本が本気で次世代技術に挑んでいる証です。
私はかつて半導体研究に携わり、日本がDRAMからプロセッサーに移行するべき時期に十分な投資を行わず産業競争力を失った場面を経験しました。その教訓からも、今の投資では「どこで勝ちに行くのか」を明確にすることが不可欠です。TSMCはすでに米国で2ナノ半導体の量産体制を整えており、生産規模では競えません。日本はニッチ市場での強みを活かす戦略が求められます。
ラピダスの生産拠点に最適な産業や用途を見極め、確実な需要先を確保することが重要です。2ナノ単体ではシステムは成立しないため、3Dパッケージングなどの周辺技術と組み合わせた差別化が必要です。
この挑戦は政府だけでは不十分で、産業界の積極的な関与が不可欠です。将来需要を見据え、恐れずに投資し、政府と産業界が一体となって取り組むことで初めて、日本の半導体は世界で存在感を保ち続けられるはずです。こういった社会の大きな流れが、未来の研究者の心を打つかもしれません。
研究者に求められる社会的責任と成果意識
— 社会的な投資と挑戦が行われる中で、研究者はどう在ればいいでしょうか。
政府や産業界が次世代技術に大規模な投資を行っても、その成果を社会に還元できるかどうかは、最前線で研究を担う人々の姿勢にかかっています。だからこそ、研究者には自らの社会的責任と成果への意識が求められます。
研究費は公的資金や企業からの支援で成り立っています。研究進める上では、研究者の好奇心や日々の楽しさを原動力にする考えは否定しませんし、研究者の真実を掘り下げる姿勢は尊重すべきです。しかし「好きなことをやるだけ」では不十分です。特に工学分野では、成果がどのように社会実装や産業応用につながるのかを常に意識し、産学連携を通じてその可能性を広げる必要があります。
最近、私は量子分野の研究にも携わっています。量子研究には政府から非常に大きな予算が投じられていますが、それは純粋な基礎研究のためではなく、産業化や日本の社会・産業力を強化することを目的としています。この背景を理解し、「研究は自己満足のためではない」「結果を出すことも責任の一部である」という意識を持つことが重要です。研究者は、与えられた資源と信頼に応える成果を目指すべきだと考えています。
産学連携を成功に導く、事前調査と産連本部の活用
— 研究を意識的に産業へつなげる機会が必要ですね。
研究者が成果を社会に届けるには、自らの意識だけでなく、それを実現する仕組みが必要です。その代表的な方法が、企業と大学が協力し合う産学連携です。
産学連携では、最初の接点づくりが成果を大きく左右します。企業が事前に論文や発表内容を確認せずに面会を設定すると、研究者の専門分野と企業ニーズがかけ離れ、初回ミーティングが時間の浪費に終わることもあります。特定の課題やテーマで面談する場合は、研究者の論文や学会での発表内容などを必ず確認すべきです。
また、直接研究者に連絡するのではなく、大学の産学連携本部(産連)を通すことも推奨します。産連にはURA(リサーチ・アドミニストレーター)が在籍し、企業の課題や予算に応じて適切な研究者をマッチングしてくれます。産連本部がワンストップで相談を受け、最適な教員との面会をアレンジできる体制をもつ大学も数多くあります。
近年、大手企業でもR&D部門において新技術開発の要求が高まっていますが、担当者が必ずしも専門分野に詳しいわけではなく、論文調査すら行わず大学訪問に至る例もあります。こうした場合こそ産連が有効で、知識や時間の不足を補い、初期のミスマッチを防ぐことで、円滑な協力関係を築くことができます。
日本全体で強みを結集する産学連携モデル
— 益先生は東工大の学長時代に産学連携機能を強める取り組みをされていました。この強化によって期待される研究業界へのインパクトとは何でしょうか。
個々の案件で成果を出すことは大切ですが、その知見や仕組みを広く共有し、全国の大学や企業が活用できるモデルへと高めていくことが、産学連携を持続的に発展させる鍵となります。
東京工業大学(現東京科学大学)では産学連携本部の機能を強化し、大規模案件の獲得に向けた体制を整備しました。初期予算設定の段階から企業に「適切な投資規模」の重要性を伝えることが、長期的な成果につながります。
地方大学は産学連携を望んでいても、企業との直接的なパイプを持たない場合が多く、東京科学大学が橋渡し役となることで、企業と地方大学をつなぐ仕組みが機能します。室蘭工業大学や九州工業大学が属する地域では、市の産業局も産学連携に意欲的で、企業ネットワークを拡大する可能性が大きいです。広範囲に産学連携を強化している東京科学大学のような大学と連携して、連携大学の一つが窓口となり案件を橋渡しする体制が有効となります。研究費の流れも柔軟にし、URA人件費分を確保しつつ地方大学に研究資金を流す枠組みを構築すれば、情報やネットワークそのものが価値となり、モデルとして成立すると思います。
さらに、この連携は東京科学大学にとっても大きなメリットをもたらします。地方大学と結びつくことで、地域に根ざした研究者や多様な専門分野の人材を活用でき、研究力の層が厚くなります。また、これまでアクセスしづらかった地域企業や産業課題とも結びつき、共同研究の可能性が一層広がります。つまり、地方大学にとっては企業との接点が拡大し、東京科学大学にとっては人材と研究テーマが拡充されるという、相補的な関係性が形成されるのです。
日本の大学は規模が小さく、単独で世界と戦うのは困難です。東京科学大学も学生数はMITと同規模ですが、研究者数は約10分の1にとどまります。ゆえに、大学ごとの強みを結集し、日本全体でWin-Winの関係を築くことが重要です。特に理工系大学間では、すべての大学が個別に産学連携機能を持つ必要はなく、東京科学大学のようないくつかの大学が集約的にその機能を担う方が効率的です。
また、大学だけでなく、国立研究開発法人産業技術総合研究所に新設されたG-QuATも、国内外の企業との共同研究や企業独自の研究に活用できる開放型設備として整備されています。これは単独あるいは共同で、世界のさまざまな社会課題を解決するために設立されたものです。
複数の大学、研究所、企業がそれぞれの専門性を持ち寄り、組み合わせることで、競争力を高めていくことが不可欠だと考えています。もしこインタビューを読んでいる研究者の方で興味を持った方がいれば、ぜひG-QuATで画期的な研究に取り組んでいただきたいと思っています。
※ 次回の後編では、引き続き益一哉先生に、研究者のキャリア形成についてお話を伺います。
株式会社CoA Nexus編集部 コメント
益先生とのインタビューを経て、産業界においても人材流動性を高めることは、日本全体の研究力と産業競争力の底上げに直結することを再認識しました。これまで研究開発領域に特化した事業を展開しておりましたが、企業が積極的に人材の往来を促すことは、単なる採用や配置の最適化にとどまらず、アカデミアと産業界の双方に新しい視点や技術的なシナジーをもたらすという考え方はわたしたちに取っても新たな気づきでした。
この動きが広がれば、大学から企業、企業から大学への移動が自然なキャリアの選択肢となり、研究成果の社会実装がより迅速かつ多角的に進むと考えています。
私たちは、こうした好循環の実現には「接点づくり」と「相互理解」が欠かせないと考えています。研究者と企業が互いの強みを認識し、適切なマッチングを通じて協働できる環境を整えることが、次世代技術の開発スピードを高め、ひいては日本の研究・産業全体の持続的な成長につながると確信しています。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。