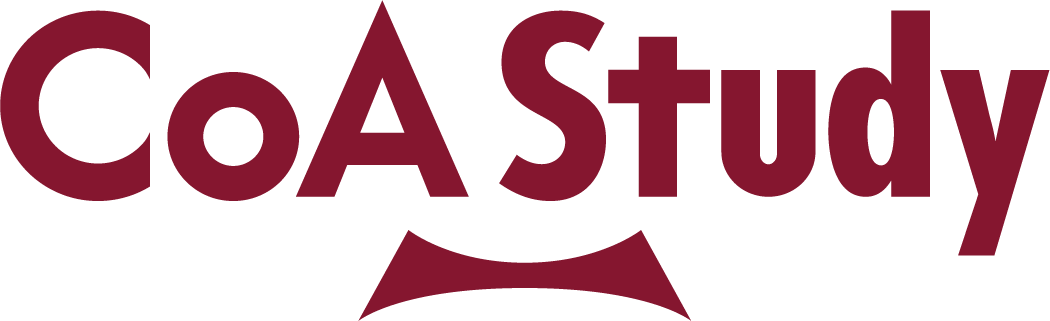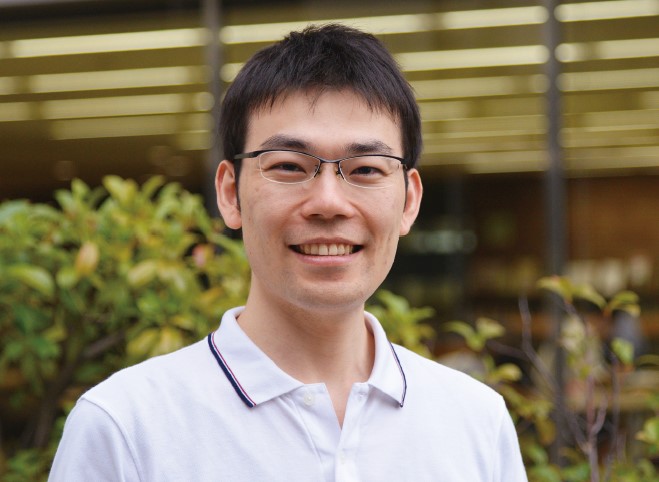異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。
若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。
リスペクトリレー企画第1回の後編では、前編に引き続き、電子デバイスおよび集積回路工学の第一人者であり、東京工業大学(現・東京科学大学)の前学長で、同大学名誉教授の益 一哉(ます かずや)先生にお話を伺います。 本編では、日本の研究力強化に尽力されてきた益先生に、研究者のキャリア形成や次世代人材の育成について語っていただきました。
研究に必要なのは、成果を待てる環境
— 現在の大学における人材育成や研究者支援について、先生は何が大切だと考えていらっしゃいますか?
私が研究者になった当時、東北大学には「論文を量産する」よりも、本質を見極めて世の中の方向を変えるような研究を目指す文化がありました。流行のテーマに飛びつき短期的に成果を出すことよりも、時間がかかっても価値あるテーマに挑む姿勢が重んじられていました。
しかし近年では、論文数をKPIとして設定し、「小さな研究でもよいから100本書けば1本は成功する」という考え方が広がっています。こうした取り組みも努力の一形態として否定はしませんが、社会の方向性を変えるような研究には時間を要するのも事実です。
わたしが助教授になったのは39歳と、同世代より少し遅い時期でした。その背景には、大学で進行していた半導体スーパークリーンルーム建設プロジェクトへの関わりがあります。当時、日本でも最初期となるこの施設の設計や計画提案など事務的な業務を多く任され、研究がほとんど進まない期間が続きました。とはいえ、与えられた役割を真摯に果たしていたことは周囲にも理解され、「結果が出るまで待とう」という雰囲気があったのです。
昔は、研究には時間がかかることを受け入れ、成果が出るまで待ってくれる環境がありました。人を育てるには時間が必要です。もちろん、待っても芽が出ない人もいれば、粘り強く成果を残す人もいます。今は任期もある中で短期間で成果があげられるテーマを選定する傾向があることも理解はしていますが、大学側には改めて「待つこと」の大切さを認識してほしいと思っています。
一段上の視点が研究や教育の捉え方を変える
— 時間をかけられたからこそ、得られた経験や身につけられた力はあるでしょうか?
「成果を待つ」文化は、研究者としての成長だけでなく、より高い視点を身につける土壌にもなります。
当時は教授がテーマを提案し、皆で議論を重ねた後、最終的な研究計画書(プロポーザル)を教授と共に仕上げ、科研費の申請を行っていました。
この経験は、後に大規模な科研費を獲得する際に大いに役立ちました。教授の立場を想定して申請書を書いていたため、「この程度の計画では偶然でも採択されない」と厳しく指導され、計画の質を徹底的に磨く習慣が身につきました。
そのため、自分が教授として申請書を書くようになっても、特別な違和感はありませんでした。立場が変わっても、やるべきことは同じだったからです。
この経験を通じて学んだのは、「一段上の視点で物事を見る」ことの重要性です。多くの人は、助手やポスドクとして自分の立場から次のことを考えがちですが、上の立場から全体を見渡し、「この人をどう育てるか」という視点を持つことは、教育や組織運営に大きな影響を与えます。私は、その視点を教えてもらえたことを、今も大きな財産と感じています。
異なる環境で磨かれる柔軟性と粘り強さ
— 以前に比べて即時性が要求される研究環境において、現在の研究者は日々目前の業務に追われている印象があります。若手研究者が視野を広げるためにはどのようなアクションを起こせばよいでしょうか。
視野を広げる方法は立場を変えて見ることだけではありません。環境そのものを変えることも、大きな成長をもたらします。
若手研究者には、今いる環境だけでなく、異なる条件下での研究も経験してほしいと思います。環境が変わることで、視野や発想は大きく広がります。特に長期の海外留学やポスドク経験は、研究者としての成長を大きく促します。私の印象では、海外で2〜3年ポスドクを経験した人は、柔軟性と粘り強さを備えた、非常にたくましい研究者になっています。新しい文化や研究環境で生き抜く力は、帰国後の活動にも大きな強みとなります。
これは高専出身者にも共通しています。15歳という若さで工学や技術の道に進む決断をした時点で、大きな一歩を踏み出しており、その決断力や行動力は将来の研究活動を支える重要な資質です。
現在の日本では、博士号を取得しポスドクとして活動していれば、よほどの事情がない限り職は見つかります。しかし、単に生き残るだけでなく、突き抜けた成果を出すには、もう一段の努力が必要です。それは「耐える力」です。困難や不安定さの中でも研究を続け、環境の変化や人間関係の摩擦を乗り越える粘り強さこそが、長期的な成功をつかむ鍵だと感じています。
研究は完璧な準備より、アイデアと行動力、人とのつながりが鍵
— 環境選びと同様に、研究テーマの選択も研究者の在り方に影響する気がします。 益先生は研究テーマを選ぶ際に、どのような姿勢や考え方を大切にされてきましたか?
私は「昔からこの研究をやりたかった」や「強い信念を持って取り組んできた」というタイプではありません。信念は明確に定義できるものではなく、その時々に「面白い」「よく分からないけれど気になる」と感じたテーマに取り組む積み重ねでも良いと考えています。
もちろん「科学の真理を追究する強い志」を持つことは素晴らしいですが、全員がそうである必要はありません。強い信念がなくても、好奇心や日々の楽しさを原動力に研究者として活動することはできます。私は大学での研究において、特に「キュリオシティードリブン(好奇心駆動)」の姿勢を大切にしてきました。
例えば、研究室にあった分子線エピタキシー(MBE)装置を後輩が使っているのを見て、「やってみよう」と声をかけ、一緒に実験を始めたことがあります。また、自分の研究室の装置では測定できない項目があった際には、知り合いの研究室に相談し、古い装置を借りて測定を行いました。ときには先生の知らないところで実験をしていたこともありました。それだけ柔軟でスピード感のある環境だったのです。
この経験から、研究は必ずしも完璧な準備から始める必要はなく、アイデアと行動力、人とのつながりがあれば実現できることを学びました。多少型破りでも、熱意を持って動けば新しい成果につながります。この「スピード感」と「柔軟さ」は、アカデミアでも企業でも共通して重要な資質であり、キャリア選択においても、自分がどう動き、周囲のリソースをどう活かせるかが鍵になると考えています。

研究の芽は、人との出会いから生まれる
— 「人とのつながり」というキーワードが出てきましたが、研究者同士のネットワーキングにはどういった価値があるでしょうか。
行動力と柔軟さは、研究室の中だけで完結するものではありません。外に出て人とつながることで、新しいテーマや発想が生まれ、研究の幅は一気に広がります。
研究を発展させるためには、自分の分野に閉じこもらず、異分野や異なる立場の研究者との交流が欠かせません。加速度センサーの研究がパーキンソン病への応用につながったのも、異分野の先生との何気ない会話がきっかけでした。
学会や会議では、普段参加しない分科会に顔を出す、別分野の国際会議に学生を同行させるなど、意識的に新しい場に足を運ぶことが、自分の研究の幅を広げるチャンスになります。
特に、同世代だけでなく上の世代とのネットワークも重要です。1980年代後半から2000年くらいにかけて、東北大学の大見忠弘先生、広島大学の廣瀬全孝先生らが主導した大学間合同研究会があり、教授陣と若手研究者、学生が交流する場があり、そこでのつながりが共同研究や採用にもつながりました。懇親会は単なる飲食の場ではなく、多くの人と会話する機会です。特別な話題がなくても、「博士課程に進めと言われていますが、先生はどう思われますか?」 のように率直に質問すれば、思わぬ有益な助言が得られることがあります。
学生時代は、一生のうちの限られた特権的な期間です。遠慮せず多くの人に話を聞くべきです。私自身、博士課程のときに思いついた新しい材料研究は当時所属していた研究室内ではあまり反応がありませんでしたが、他大学の先生に相談すると「それは面白い、やってみたら」と背中を押され、そのテーマで2〜3本の論文を発表できました。
研究の芽は、意外な出会いや会話から生まれます。そのチャンスを逃さないためにも、人と会い、話す機会を大切にしてください。
研究の現場では、確かな計画や技術力と同じくらい、行動力と人とのつながりが成果を左右します。思いついたアイデアを素早く形にし、必要なリソースや知見を持つ人に自ら働きかける姿勢は、アカデミアでも産業界でも共通して求められる資質です。
※ 益一哉先生へのインタビューはこちらで終了ですが、「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」はまだまだ続きます。 本企画では、卓越した才能を備えた研究者を発掘・可視化し、分野を越えた信頼のネットワークと好循環を生み出すことを目指しています。 次回は、益先生が推薦する研究者にお話を伺います。どうぞご期待ください!
株式会社CoA Nexus編集部 コメント
研究を進める中で、ときには異分野や異なる立場の研究者との交流が大きな成果につながります。益先生の加速度センサーの研究がパーキンソン病への応用につながったのも、異分野の先生との何気ない会話がきっかけでした。こうした偶然の出会いは、日常の延長線上では生まれにくく、意識的に外に出ることで得られるものです。インタビューの中で、益先生から学会や会議では、普段参加しない分科会に顔を出す、別分野の国際会議に学生を同行させるなど、自らの専門領域を越えて新しい場に足を運ぶことが、自分の研究の幅を広げ、異なる視点を取り入れる大きなチャンスになると教えていただきました。
一方で、研究活動には必ず困難や不安定さが伴うと思います。計画通りに進まない時期や、環境の変化、人間関係の摩擦など、続けること自体が試される瞬間は少なくありません。そうした局面で鍵となるのが、状況に耐えながら挑戦を続ける「耐える力」なのではないかと改めて考えさせられました。成果が見えず「いつまで耐えればよいのか」と迷う場面もあるでしょうが、そのような辛いときこそ積極的に他の人と交流することが、行き詰まりを打開し、新しい成果やつながりを生み出すきっかけになるかもしれません。
私たちは、こうしたネットワーク形成と行動力、そして耐える力を後押しする環境を、研究者と企業の双方が協力して整えていくことが、日本の研究力と産業競争力の強化に欠かせないと考えています。分野や立場を越えた出会いの場を増やし、互いの強みを活かした協働を促進すること。それこそが、次世代技術の創出や社会課題の解決を加速させる原動力になると確信しています。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。