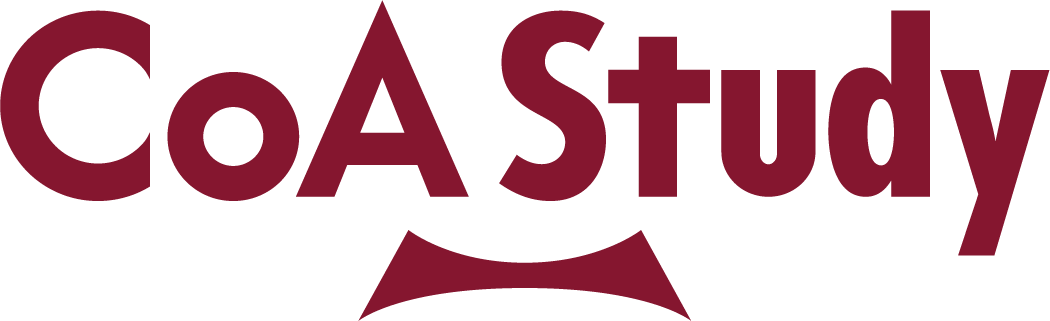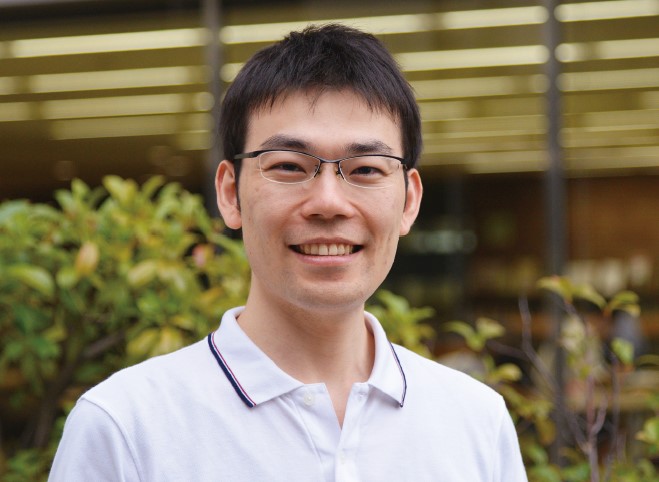異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。
若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。
リスペクト・リレー企画第2回では、2024年のノーベル化学賞によりタンパク質研究が世界的に注目を集める中、この分野の最前線で活躍する研究者、東京科学大学 情報理工学院 情報工学系 准教授・大上雅史(おおうえ まさひと)先生に登場いただきました。
創薬分野におけるAI活用の未来や、研究への向き合い方について伺っています。
■プロフィール
大上 雅史(おおうえ まさひと)先生
所属:東京科学大学 情報理工学院 情報工学系 准教授
タンパク質間相互作用予測ソフトウェア「MEGADOCK」の開発を中心に、バイオインフォマティクスとスーパーコンピューティングを融合させた研究を展開。
創薬研究の「武器」を増やす計算ツール開発
— 現在の研究内容についてお聞かせください。
私が主に取り組んでいるのは、計算機を用いて薬となり得る分子を設計する研究です。新薬の開発には現在、1000億円以上、10年以上という膨大なコストと時間が必要とされており、その負担をいかに軽減できるかを意識しながら研究を進めています。
計算によって予測した分子がそのまま薬として利用できれば理想的ですが、現実にはそう簡単ではありません。動物実験や臨床試験を経て、安全性や有効性を確認しなければ薬として世に出すことはできません。しかし、計算技術の精度が高まれば、より確度の高い分子設計が可能になると考えています。
その取り組みには、近年のAI技術も積極的に導入しています。たとえば、DeepMindが開発し、2024年にノーベル化学賞を受賞した「AlphaFold」のようなソフトウェアは、創薬研究を支える有力なツールの一つです。私自身の研究でも、薬効の予測や特定の作用を持つ分子設計などに向けた計算ツールを数多く開発してきました。
ただし、薬の開発は非常に複雑です。毒性の有無や効果の有無に加え、どの疾患に効くのか、さらにはどの患者に効くのかといった要素が絡み合っています。疾患には多様なタイプが存在し、ある患者には有効でも、別の患者には効かないこともあります。私たちが「タスク」と呼んでいる、ケースバイケースの条件が無数に存在しています。
だからこそ、多様なタスクに対応可能なツールを増やし、研究者が使える武器を充実させることが、私の研究の中心テーマです。
— 研究の中で開発された MEGADOCK についてもお聞かせください。
MEGADOCKは、タンパク質間相互作用(PPI)を高速に予測するソフトウェアです。私は学部生の頃からこのテーマに取り組んでいました。当時は、タンパク質同士が相互作用するかどうかを一組ずつ計算するのに約2時間を要しており、100組なら200時間、1万組では実に2万時間もの計算時間が必要と考えていました。これでは実用的とは言えません。
そこで、「MEGA」という名前が示すように、100万ペア規模の相互作用を現実的な時間(およそ1日)で予測できることを目指しました。並列化技術やGPUの活用などを通じて高速化を実現し、その成果は2014年にまとめた私の学位論文にもつながっています。
その後、AlphaFold が登場すると、状況は大きく変わりました。AlphaFoldによってタンパク質の立体構造が高精度に予測できるようになったことで、MEGADOCKの使い方も広がってきました。現在ではMEGADOCK単体での利用に加え、AlphaFoldの結果と組み合わせて解析を行うアプローチも提案しています。両者を組み合わせることで、これまで以上に高精度な相互作用予測が可能になり、そこからさまざまな応用や研究の発展が生まれると考えています。
AIの真の強みは、人間が気づかない関連性を見つけ出す「連想ゲームの加速」
— MEGADOCKやAlphaFoldの活用によって応用範囲も広がってきたとのことですが、特に抗体医薬品など複雑な分子の創薬研究にはどのような影響を与えるとお考えでしょうか。
これは実は一番説明が難しい部分です。AIを導入すると「創薬は何年短縮できるのか」「どのくらい効率が上がるのか」とよく尋ねられますが、具体的な数字を示すのは非常に難しいです。
例えば、新しい高性能の顕微鏡を開発したとしても、「この顕微鏡のおかげで創薬が何年早まる」とはなかなか言えませんよね。それと同じで、AIの技術も創薬の加速に確実に貢献しているものの、「2年短縮できる」「100億円削減できる」といった定量的な効果を明言するのは難しいのが現状です。
ただ、この10年で計算機の性能は劇的に向上しました。スーパーコンピュータは「10年で1000倍速くなる」と言われていますし、一般的な計算機も着実に高速化しています。その結果、以前は小さな分子しかシミュレーションできなかったものが、今では抗体分子レベルでも動的な挙動を気軽に計算できるようになってきました。つまり、少しずつスケールを拡大しながら、抗体医薬の研究開発にも計算技術の力が及びつつあると考えます。
— そうした流れの中で、AI創薬が、ヒトがこれまで考えつかなかった創薬モダリティや自然界で見つかっていない分子構造を発掘する可能性はあるのでしょうか。
正直なところ、まだ課題は多いと考えています。根本的な問題として、AIは既存のデータに基づいて学習するため、人類がまだ観測していない現象や、データとして蓄積されていない情報を再現することは困難です。ChatGPTが存在しない言語を話せないのと同じ原理ですね。
現在、多くの成功例として挙げられているのは、既存の実験データや観測結果から論理的に類推できる範囲での新発見です。つまり、「これまでの知見を総合すると、こうなるはずだ」という三段論法的なアプローチで新しいものを見つけるケースが大半を占めていると考えています。
しかし、AIの真の価値は「連想ゲームの加速」にあると私は考えています。膨大なデータの中から人間では気づかない関連性を見つけ出し、それを高速に処理することで、これまで治療法が見つからなかった疾患に対して新たなアプローチが開ける可能性があります。完全に未知のものを創り出すのではなく、既存の知識を効率的に組み合わせて新しい解決策を導き出すことにこそ、AIの最も得意とする力があるのではないでしょうか。
共同研究成功の鍵は、成果の扱いの事前調整
— 近年、共同研究が増えているとのことですが、研究パートナーはどのように見つけられているのでしょうか。また、実際に共同研究を進める際に大切にされている点についてもお聞かせください。
基本的には、先方からお声がけいただくことがほとんどです。時代が私の研究分野への需要を高めていることもあり、私自身は運が良かった面もあるのかもしれません。
ただ、「AI創薬」や「タンパク質の立体構造計算」を相談できる研究者として名前を挙げていただけるようになったことが、共同研究の増加につながっていると感じています。学会発表を積極的に行い、成果をオープンにしてきたことで、「どこかで見かけた」というケースが増えているのではないでしょうか。
共同研究を進めるうえで最も重視しているのは、成果の扱いを事前に相談することです。たとえば、学生が参画する場合には学生が発表できる内容でなければ困りますし、論文化したいのか秘匿したいのかといった方針の食い違いが起きてしまうとお互いに不幸です。予算の話以上に、こうした権利関係のすり合わせが重要だと考えています。
私の分野の場合、基本的には人件費とスーパーコンピューターの使用料程度で済むため、予算面はそれほど複雑ではありません。現在は規模の小さいものから大きなものまで含め、民間企業やアカデミア合わせておよそ30件ほどの共同研究を並行して進めている状況です。
研究要素のある技術は大学、完成度の高い技術は事業化
— 研究成果の扱いや権利関係のお話を伺いましたが、先生ご自身も起業をされていますね。創業の経緯や、その過程で特にご苦労された点についても教えていただけますか。
共同研究と似た話ですが、起業に関しても大学との権利関係が複雑化しがちです。MEGADOCKについては研究要素がそれほど多くなく、むしろサービスとして位置づけられると判断し、事業化に踏み切りました。基本的には、研究要素を含む新しい技術は大学で扱い、完成度の高い技術は事業として切り分けるようにしています。
最も大変だったのは、社会常識をあまり知らなかったことです。これは研究者にありがちな点かもしれません。会社設立に資金が必要なことや、毎年決算を行わなければならないといった基本的なことから、会社法や会計の知識まで、持っていて損はないなと痛感しました。
もちろん専門家に相談するのですが、ときには取り返しのつかない落とし穴のようなものもあります。伴走してくれる方がいると非常に心強いので、会社法や企業経営についてアドバイスできる方と一緒に進めることをお勧めしますし、そのようなサポート体制が大学に備わっていると、大学発スタートアップももっと増えていくと思います。
境界領域に着目することで独自性の高い研究を実現
— 起業のお話からも、研究と事業をどのように切り分けるかを強く意識されていると感じました。では、研究そのものに目を向けたとき、先生が研究テーマを選ぶ際に特に重視されていることは何でしょうか。
私が学生だった2010年前後は、タンパク質の立体構造計算はそれほど注目されていませんでした。当時はゲノム解析が主流でしたが、そのブームが落ち着いた頃にAlphaFoldのようなAI技術が登場し、再びこの分野が注目されるようになりました。これは運が良かった面もありますが、重要なのは常に広い視野を持つことだと考えています。
私はもともとコンピュータサイエンスの学科に所属しており、情報分野の知識を生物学や創薬にどう結びつけるかが課題でした。一つの分野に閉じるのではなく、境界領域や周辺分野に目を向けることで、独自性や発展性の高い研究につながると思います。現在はAI技術がさまざまな分野で活用されていますが、だからこそ境界領域で柔軟に活躍できる研究者が求められていると感じています。
— 先生ご自身が大切にされている広い視野や境界領域へのアプローチは、研究室での学生のテーマ設定にも影響しているのでしょうか。実際に学生さんの研究テーマはどのように決められているのですか。
基本的に、うちの学生のテーマはみんなバラバラなんです。同じ研究をしている学生は基本的に一人もいなくて、それぞれ違うテーマに取り組んでいますが、研究領域としては大きく共通しています。
たとえば、免疫細胞が生成する抗体が血中でどのように分布するかを予測する研究をしている学生もいれば、まったく異なるテーマとして、金属クラスターでの触媒をどう作るかを探究している学生もいます。本当に多様ですが、それぞれに研究の必然性があります。
テーマの決め方としては、「何かできそうなことが見えてきたときに、それをどう解決していけるかを考える」という流れが基本だと考えています。共同研究をベースに考えることも多く、例えば現在進めている1型糖尿病のプロジェクトでは、「免疫状態を改善できれば治療につながるのではないか」という仮説から出発しました。そこで「免疫状態を改善させる物質は何か?」という問いが生まれます。
免疫原性を持つタンパク質が候補になりますが、そのままではアレルギーの原因となってしまいます。そこで「アレルギーの原因となり得るタンパク質の断片を利用すれば免疫状態を変えられるのではないか」と考えます。そこから、「タンパク質の断片の免疫原性が計算で予測できれば、実験に依存せずに研究を加速できる」と思い至り、新しい研究テーマとなりました。
このように、プロジェクトの中で必要とされる技術を生み出す形で研究テーマが決まることが多いです。やっていることはバラバラでも、共通しているのは「情報科学を活用して、今は存在しないけれど少し頑張れば実現できそうな道具を作る」こと。それをみんなで追求している研究室だと思います。
オープンにすることで広がる研究の可能性
— 多様なテーマに取り組む中で、実際に成果につなげていくために意識されていることは何でしょうか。
私が意識しているのは、研究成果をできるだけ早くオープンにすることです。理由はいくつかあります。まず、研究活動の活発さを示すことはキャリア形成に有利だと考えています。また、計算ツールや手法は多くの研究者が同時並行で取り組んでいるため、早めに共有したほうが分野全体の発展を加速できると考えています。
発表の場は論文や学会に限られません。近年ではSNS(X)を通じたコミュニケーションも非常に有効だと考えています。例えば、新しいソフトウェアを使っていて困ったことを投稿すると、他の研究者が解決策を教えてくれることもあります。興味深い事例として、私の旧来の友人でもある森脇由隆 准教授(東京科学大学)は、AlphaFold関連のノウハウを積極的に旧twitterで発信していたところ、そのツイート自体がDeepMindの論文で引用されたことがありました。ツイートが論文に引用されるという現象は、オープンサイエンスの新しい広がりを示していると感じます。
研究業績を評価する際、論文は依然として重要な指標の一つです。もちろん質も大切ですが、数も含めた総合的な評価がなされる傾向があるため、バランスよく成果を積み重ねることに意味があると考えています。私自身も、できるだけ早く発表することを心がけてきました。早めに発表すれば論文数も自然に増えていきますし、学生時代に日本学術振興会 育志賞をいただいた際も、5〜6本の論文実績があったことが評価に多少なりとも影響したのではないかと思います。一つ一つは大きな成果ではなくても、積み重ねを通じてどのような研究を目指していくかが重要だと感じています。
— 最後に若手研究者へのアドバイスをお願いします。
境界領域を恐れないことが一番大切だと考えます。知らない分野だからと逃げずに興味を持って取り組めば、発展性の高い研究につながります。
キャリア面では、論文数は定量的評価材料として持っておいて損はありません。また、学会発表を積極的に活用してください。特にafterコロナの傾向として、学生のリアルなプレゼンテーションの機会が少なくなっていると感じます。プレゼンテーション能力向上のチャンスとして、意識的に学会発表を行うことをお勧めします。
株式会社CoA Nexus編集部 コメント
大上先生のインタビューを経て、境界領域や周辺分野に目を向けることで研究の独自性と発展性が高まるということを実感しました。創薬研究における計算科学やAIの活用はまさに異分野融合の典型であり、従来の枠組みにとらわれない視点が新たなブレイクスルーを生み出すことを示していると感じました。
また、異分野の知見やふとした出会いから生まれる優れた才能との協働が、研究にこれまでにない視点と可能性をもたらすという考え方は、私たちCoA Nexusの事業観とも深く重なります。研究者同士、あるいは研究者と企業が交わる場においてこそ、新しいアイデアや挑戦が芽生え、社会実装へとつながる道が拓かれると考えています。
私たちは、こうした知の交差点を意識的に設計し、研究者と産業界の間に新しい接点を生み出すことで、日本全体の研究力と産業競争力を高める循環を支えていきたいと思います。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。