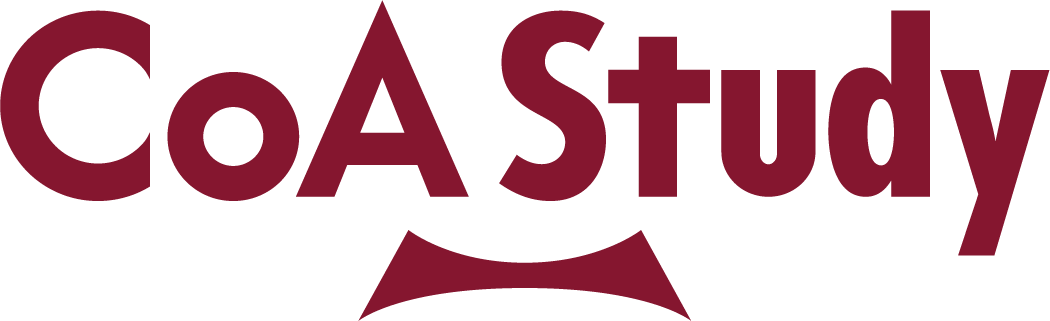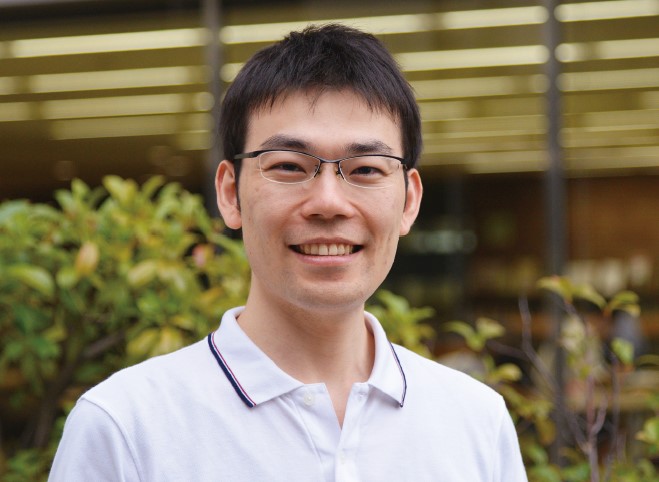異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。
若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。
リスペクトリレー企画第3回では、AIの普及にともない一層の通信速度が求められる次世代無線通信技術の最前線でご活躍されている、東京科学大学 工学院 電気電子系 教授・岡田健一(おかだ けんいち)先生にご登場いただきました。
無線技術を中心に半導体領域の未来や研究への向き合い方について伺っています。
■プロフィール
岡田 健一(おかだ けんいち)先生
所属:東京科学大学 工学院 電気電子系 教授
次世代無線通信技術に向けたミリ波無線回路、アナログ・デジタル混載回路に関する研究を行っています。
アナログ回路設計の「民主化」を目指して
— 現在の研究内容についてお聞かせください。
現在、私たちは複数の研究を並行して進めていますが、そのすべての根幹にあるのは半導体技術です。とりわけ、CMOS(シーモス:Complementary Metal Oxide Semiconductor)を基盤としたLSI(大規模集積回路:Large Scale Integration)技術による通信分野の研究領域は、日々拡大を続けています。
無線技術の研究開発に関しては、大きく二つの方向からアプローチしています。ひとつは要素技術の研究であり、発振器、電力増幅器、低雑音増幅器、周波数変換器、AD変換器といった基礎的な回路ブロックの性能を徹底的に追究する取り組みです。もうひとつは応用研究で、これらの要素技術を組み合わせ、実際の無線機として大規模なシステムを構築する研究です。両面からのアプローチによって、技術の深化と実用化の双方を追求しています。
研究対象は幅広く、5G・6G向けに「ミリ波」と呼ばれる高周波数帯を用いた無線機の開発を行う一方で、わずか1ミリワットで動作する超低消費電力Bluetooth ICの研究にも取り組んでいます。周波数帯域としては、1GHz以下から300GHzまで実に広範な領域をカバーしています。純粋な学術的関心に基づくテーマもあれば、5Gや6Gといった技術動向に応じて企業との共同研究を進めているものも数多くあります。
より高い周波数帯になると、私自身の学術的興味に基づくテーマや、将来を見据えた先行研究としての取り組みが中心になります。他方で、社会的要請に応える形で進める企業との共同研究も重要です。初期にはソニーや富士通研究所と研究を開始し、その後もNTTと長期にわたって連携を続けています。近年は再びソニーと新たなテーマに挑戦しているほか、5G関連ではシャープ、さらにパナソニックとはテラヘルツ帯といった超高周波領域での研究を進めています。
また、私個人の関心としては、集積回路で実現可能な限界に近い300GHz帯への挑戦があります。通信速度においては、従来100~120Gbps程度だったものを、昨年は一気に640Gbpsまで引き上げることに成功しました。こうした研究は技術的なブレイクスルーを目指すと同時に、「驚きを与えたい」という思いも込められており、日々新たな挑戦を続けているところです。
― 無線通信の分野では、短距離にとどまらず、長距離での実験にも取り組んでいらっしゃいます。具体的にどのような試みでしょうか。
現在、100Gbpsの高速通信を約10kmという超長距離にわたり無線伝送することに挑戦しています。
東京科学大学から東京タワーまではおよそ10km弱の距離があります。研究室から東京タワーが見えることから、「実際に電波が届くのではないか」と考え、実験を計画しました。さらに視点を広げると富士山も見えるため、「富士山まで届くのか」という挑戦も検討しています。
加えて、さらなる挑戦として、地球と月との間での通信にも関心を寄せています。5Gや6Gの潮流の中で衛星通信は急速に拡大しており、その延長として「より長距離の通信」の可能性を探究しているのです。現在、米国のアルテミス計画など月探査で用いられているネットワークは、数Mbps程度のデータレートにとどまっています。しかし、私たちの試算では、1Gbps以上の通信も十分に実現可能だと考えています。
将来的には、他大学の研究者や機械系の先生方と協力し、月面に仮想巨大アンテナを設置して地上との通信を行う構想も視野に入れています。これは純粋な学術的関心から生まれた挑戦であると同時に、技術的にも大きな可能性を秘めたテーマだと感じています。
― 挑戦的でスケール感のある研究で、ますます期待が高まりますね。一方、半導体分野においてはどのような挑戦があるのでしょうか。
半導体分野でも、近年さまざまな取り組みを進めています。通信に用いられる回路は、アナログとデジタルが融合した「アナログ・ミックスドシグナル回路」が中心です。回路分野を大きく分けると、CPUのようなデジタル回路と、クロック回路やAD変換器、通信回路などのアナログ回路があります。無線機も基本的にはほとんどがアナログの回路です。さらに、DRAMのインターフェースであるDDRや、AI用途で使われるHBMといった高速インターフェースも、根幹はアナログ回路に支えられています。
私の専門も、このような高速回路に関わる部分です。ただ、この領域は「職人技」に依存する傾向が強く、熟練した設計者にしか作れないという状況が長く続いてきました。設計知識が暗黙知のまま共有されず、特定の人だけが扱える世界になっていたのです。
そこで現在取り組んでいるのが、アナログ回路設計の知識を言語化し、暗黙知を形式知へと変換する活動です。これにより、従来は限られた熟練者しか扱えなかった設計手法を広く共有できるようにし、アナログ回路設計の「民主化」を進めたいと考えています。誰もがアクセスできる知識体系を構築することで、より多くの人がこの分野に挑戦できるようにすることが目標です。
社会実装の鍵は、高性能化と低価格化の両立
― 6Gといった次世代通信技術の実装は、私たちの生活や社会にどのようなインパクトを与えるでしょうか。
通信は社会インフラそのものですので、一気に変わるというよりは少しずつ進化していくものではないかと思います。1〜2年の短いスパンでは、スマートフォンのデータ通信がわずかに速くなったり、バックホールの帯域が改善されたりといった形で現れるかと思います。ただし、多くの人にとっては「この時間帯はダウンロードが遅いな」といった不便が少し減る程度で、劇的な変化としては気づかれにくいかもしれません。こうした日常的な不満が徐々に解消されていくことが、まず目指すべき方向ではないでしょうか。
一方で、30年ほどの長いスパンで見ると、通信速度はおよそ1000倍に達するものと考えられます。例えば、携帯電話の初期は9.6kbps程度しか扱えず、その後の初期の3Gでも384kbps、Wi-Fi初期でも11Mbps程度でした。その制約の中では音声や文字が中心でしたが、今では動画のストリーミングが当たり前になっています。
今後はさらにデータ量が増大し、特にAIの活用が進むことでデータの流れは飛躍的に拡大するのではないでしょうか。従来はクラウド側で処理していたものが、エッジでも処理可能になり、中継サーバーなどでも分散処理が進むものと考えられます。通信速度が上がることで、多様なコンピューティングアーキテクチャを許容できるようになり、その基盤を整えることこそが次世代通信技術の大きな役割ではないかと考えています。
—データ量の増加に依存した需要の高まりがあるということですが、社会実装はスムーズに進んでいくのでしょうか。
無線研究は技術的には着実に進展していると思いますが、社会実装という段階になると、やはり「商業的に成立するかどうか」が大きな課題になってきます。企業が技術を取り入れ、事業として利益を上げられるビジネスモデルを構築できるかどうかを、研究としっかり結びつけていく必要があるのではないでしょうか。
5Gもまさにその典型例だったかと思います。研究者は早くから課題を認識していましたが、社会インフラとして少しずつ整備していかざるを得ませんでした。しかも電波資源は、低い周波数帯から順にすでに埋まりつつあり、必要とされるデータレートは何倍にも増加し続けています。そのため、将来的に低い周波数帯は必ず枯渇することが予想されており、そこに向けた準備が欠かせないのではないでしょうか。
一方で、データレートを確保するためには「いくらコストをかけるのか」という問題も避けて通れません。早い段階で投資して社会実装を進めるのか、それともギリギリまで現状を使い続けるのか、その判断が問われる場面がこれから増えていくものと思われます。
その中で私が重視しているのは、性能をただ高めるだけでなく、「同じ性能をより低コストで実現する」ことです。高性能化と低価格化を両立させる技術こそが、社会実装を加速させる鍵になるのではないでしょうか。大学としても、こうした技術的基盤を提供し、社会への橋渡しを支援していきたいと考えています。
相互理解が人を動かす
―企業との共同研究を数多く手がけられていますが、共同研究の成果を最大化する秘訣は何でしょうか。
共同研究には、やはり難しさや大変な部分が伴います。たとえば科研費による研究であれば制約は比較的少なく、求められるアウトプットの性質も異なります。しかし共同研究となると、企業側が期待する成果と、研究遂行に必要な費用との間にしばしばミスマッチが生じます。そのため私は、初期の段階で大学側の状況を丁寧に説明し、十分に理解いただくことを重視しています。
加えて、学生の果たす役割も大きなものがあります。学生は論文執筆や研究活動、学業に取り組む一方で、共同研究に参画することでスキルを磨いています。すべてのテーマに学生が関わるわけではありませんが、装置の製作や実験を伴うテーマでは、多くの場合学生が積極的に参加します。その際に重要なのは、学生自身がやる気を持てるかどうかです。自ら「やりたい」と思えるテーマであれば研究は大きく進展しますが、そうでなければ成果に結びつきにくいのが実情です。
実際、企業の知見が加わり、大きな成果が期待できるテーマであれば学生は意欲的に取り組みますが、論文化が難しいテーマには消極的になる傾向があります。そのため企業側には、「学生はリサーチアシスタントとして一定の作業を担うことはできますが、本当に力を発揮するのは、研究を通じて大きな成果が得られ、それが本人のキャリア形成にもつながるときです」と説明するようにしています。
研究成果を論文として発表し、大学と企業が知見を持ち寄って共同で成果を社会に示すことは、学生にとって大きなモチベーションになります。その方向性を明確に示し、相互理解のもとで進めることこそが、最終的に成果を最大化する鍵であると考えています。大学としても、その前提条件をしっかりと説明することを大切にしています。
面白さこそ成果への近道
― 半導体を軸に据えながら多様な分野にまたがって研究に取り組まれていますが、研究テーマはどのように決められているのでしょうか。
研究は多くの場合、プロジェクト単位で進められ、期間は3年から5年程度が一般的です。予算がついている間はもちろん全力で取り組みますが、その後さらに資金を獲得して継続するかどうかは、その時点で「より深めたい」と思えるかどうかにかかっています。意欲が持てなければ自然とフェードアウトしていくことになり、その意味でもテーマの選定は極めて重要です。
研究テーマの選び方については慎重に考えています。若い先生方の中には、好奇心だけに突き動かされてテーマを決める方もいらっしゃいますが、私は少し異なる立場をとっています。助手になったばかりの頃、九州大学の安浦先生に「社会に役立つ研究と、自分が面白いと思う研究、どちらを選ぶべきでしょうか」と尋ねたことがあります。その際に先生は「役立つことをやろうとするよりも、面白いことをやった方が成果が出やすい。結果的にその方が社会に役立つ」とおっしゃり、大きな印象を受けました。
もっとも、それだけでは不十分だとも感じています。私は常に10件ほどのテーマを考え、その中から2〜3件を選ぶようにしています。その際には「面白さ」を前提としつつ、将来的に発展していく可能性があるか、論文として成果を残せるか、外部資金の獲得につながるか、といった複数の観点から判断します。すなわち、「面白い」という感覚に加え、学術的・実用的に成果を積み重ねられるかどうかを重視しながらテーマを決定しているのです。
―「面白い研究が結果的に成果につながる」というお言葉は非常に印象的です。研究テーマは成果に直結する重要な選択ということですが、集積回路分野における”優れた成果”とは具体的にどのようなものを指すのでしょうか。
分野によっては国際会議がほとんどなく、発表を希望すればほぼ採択される、採択率が80%を超えるようなケースもあります。しかし、集積回路の分野は大きく状況が異なり、国際会議で論文を採択してもらうこと自体が非常に難しいのが実情です。場合によっては、学術誌に論文を掲載するよりも難易度が高いことさえあります。
私たちがよく論文を投稿しているのは、集積回路分野を代表する国際会議「ISSCC(International Solid-State Circuits Conference)」です。この分野では、「Natureなどに論文を出すのはむしろ逃げている」と揶揄されるほど、ISSCCでの採択が重視されています。それほどまでに、この国際会議で発表することの価値は高く、毎年プログラムが公開されると、誰が採択されたのかが一目でわかる状況になっています。
さらに、採択件数のランキングも存在し、10年に一度、過去何件通したかという記録が発表されます。トップランカーとして名前が挙がるのは10年に一度あるかどうかという水準ですが、節目の年には表彰のような形で取り上げられることもあります。こうした競争的な側面も、この分野の大きな特徴のひとつだといえます。
─競争が激しく、今後も発展が期待される研究領域において、博士課程の学生は自身のキャリアをどのように描いているのでしょうか。
近年、集積回路の分野において、日本人学生の博士課程進学者がやや増加傾向にあります。私の研究室でも、修士から博士へ進みたいと希望する学生が増えています。背景には、半導体産業を国家的に推進していこうという潮流があり、学生たちもその将来性を強く感じ取っていることが大きな要因でしょう。少し前までは半導体分野に閉塞感が漂っていましたが、状況は大きく変化し、現在は将来に対する展望が学生にとって極めて重要な判断材料となっています。
もう一つの大きな要素は給与水準です。米国では博士課程を修了して半導体業界に就職すると、初任給が数千万円程度に達するケースもあり、この高待遇が優秀な人材を引き付けています。一方、日本では依然として給与水準が低く、「博士号を取得しても待遇が大きく変わらない」という状況が、学生のモチベーションにつながりにくいのが現実です。ただし近年は、国内企業においても博士人材の処遇改善が進み、初任給で1,000万円を超える例も見られるようになりました。こうした動きが、博士課程進学を志す学生の増加につながっているのは好ましい傾向だと考えています。
しかし、日本全体で見ると依然として「学歴社会」の傾向が根強く残っています。理系はある程度改善されてきていますが、文系では学位そのものが評価されにくく、18歳時点での学力のみが重視される傾向があります。これは社会にとって健全とは言えません。アジアの一部の国々にも同様の傾向が見られますが、日本もこの点を是正していく必要があると感じています。
何度でも、打席に立つ
― 最後に、研究者としてのキャリアの中で、特に印象に残っている失敗や挫折の経験はありますか。そこから得られた学びがあれば教えてください。
失敗は数え切れないほどあります。作ってみたけれど動かなかった、というのはよくあることですし、アイデアを思いついたものの、他の研究に取り組んでいる間に別の研究者に先を越されてしまった、という経験もあります。特に集積回路の場合、設計してから製造して、評価するまでに半年ほどかかるため、一度失敗すると取り戻しが効きません。そのため、事前にシミュレーションを重ねて入念に確認しますが、それでも「ここは評価が足りていなかったな」と後悔することはあります。もっとも、これは日常茶飯事ともいえるものです。
論文執筆でも同様です。「理論をもっときちんと詰めて説明すべきだった」と振り返ることは多々ありますし、そうした後悔は研究者なら誰もが抱えるものではないかと思います。
その中で大切なのは、とにかく多くの「打席に立つ」ことではないでしょうか。研究成果を形にするには数多くの挑戦を重ねるしかありません。残念ながら研究の世界には労働基準法のようなルールはなく、限られた時間の中でどれだけ集中して取り組めるかが勝負になります。もちろん「勝ちパターン」のようなものがあって、数年間続けて多くの論文を出せる時期もありますが、それが永続的に続くわけではありません。だからこそ常に新しいネタを探し、ホームランでも場外ホームランでもいいから、とにかく挑戦し続ける姿勢が大切ではないかと考えています。
―若手時代に研究で成果をあげるために特に意識してこられたことは何でしょうか。
国際会議などで他大学や海外の先生方と交流する中で、研究室の運営方法についてよく話を伺っていました。例えばアメリカでは、博士課程の学生に給料を支払うのは当たり前で、その内訳は「1/3が学生への給与、1/3が授業料、1/3が大学へのオーバーヘッド」といった形です。つまり、学生に渡す分の3倍以上を稼がなければならず、大変だなと思ったこともあります。ただ、その仕組みが研究者の求心力を生む側面もあり、国や分野によって運営のスタイルは大きく異なるのだと感じました。こうした他の先生方のやり方は、自分にとって非常に参考になっています。
そうして試行錯誤を続け、今の研究室の体制に少しずつたどり着きました。ただし、研究分野ごとに事情は違うため、私の方法がそのまま他に当てはまるわけではありません。それぞれの立場で悩みながら工夫していくことが重要です。
株式会社CoA Nexus編集部 コメント
現時点で「実現可能な限界」へ挑戦することを喜々としてお話してくださった岡田先生。面白さへの感性を閉ざさず、何度でも挑戦し続ける—それが研究成果を生む岡田先生の2つのメソッドなのだと感じます。
社会実装と隣り合わせの研究領域だからこそ、企業との連携も多くなるそうです。大学の研究室で実際に手を動かす学生が、モチベーションを維持できるよう企業との相互理解を深める動きは、些細なようでプロジェクトの将来を左右する重要なプロセスなのだと実感しました。
「面白さ」や「モチベーション」など、人の心の動きが研究成果にもたらす良い循環を改めて認識した今回のインタビュー。今後の岡田先生の挑戦に、胸が高鳴ります。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。