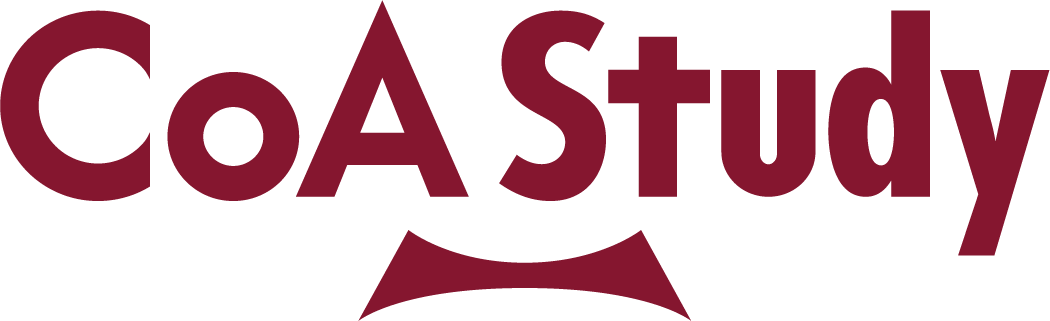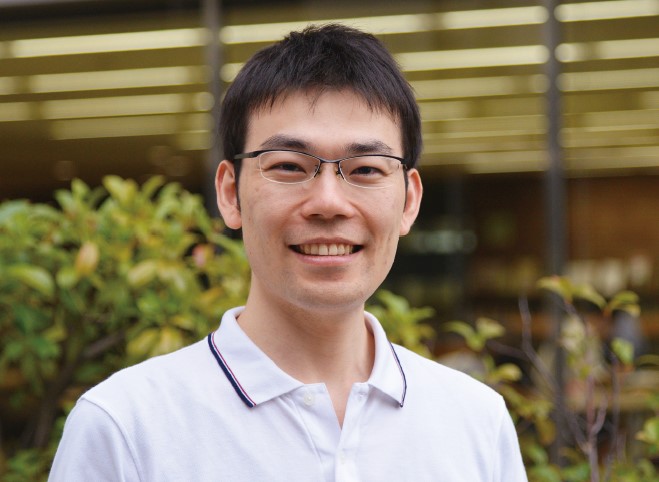異分野の知見や、ふと出会う優れた才能が、研究に新しい視点と可能性をもたらします。「トップ研究者が推薦!リスペクト・リレー」は、その分野で優秀であると認知されている研究者へのインタビューを通じて、「過去に出会った中で卓越した才能を備えた研究者」を推薦いただき、その推薦をたどりながら領域横断的なネットワークを広げていくプロジェクトです。
若手や異分野の隠れた才能を掘り起こし、信頼性ある研究者コミュニティの形成と好循環を目指します。
リスペクト・リレー第4回では、ノイズや欠損を含む複雑なデータから数学的手法によって本質的な情報を抽出・解析する研究者、東京科学大学 情報理工学院 准教授の小野峻佑(おの しゅんすけ)先生にご登場いただきました。
数理最適化とディープラーニングの関係や、研究室運営について伺っています。
■プロフィール
小野 峻佑(おの しゅんすけ)先生
所属:東京科学大学 情報理工学院 准教授
数理最適化を基盤とし、信号処理や画像解析の知見を活用することで、ノイズや欠損を伴う計測データから価値ある情報を抽出する数理的データ解析技術の研究を推進しています
数理最適化とは何か──“最適な解”で不完全データに挑む
— 現在の研究内容についてお聞かせください。
私の研究のベースになっているのは、「数理最適化」と呼ばれる技術です。少し聞き慣れないかもしれませんが、簡単に言うと“与えられた条件のもとで最も適した答えを見つける”ための数学的な手法です。たとえば、物件探しをイメージすると分かりやすいかもしれません。「1LDK」「駅から徒歩10分以内」「バス・トイレ別」といった条件の中で、家賃が一番安い部屋を探す──こうした発想を、数式に落とし込んで厳密に扱うのが数理最適化です。
実際の研究では、制約条件のもとで目的関数を最小化または最大化する“最適な解”を求めます。そのために問題をどう設計するか、どうアルゴリズムで解くか、さらにその理論的な保証をどう与えるか──そこまでを含めて研究対象になります。この技術は、私が関わっているものだけでも、リモートセンシングからバイオイメージングまで、本当に幅広い分野で使われています。
たとえば衛星観測の世界では、特殊なカメラで地表を撮影しますが、得られる画像が常に鮮明とは限りません。大気のゆらぎや光学系の制約などでノイズが入り、ボケや歪みが生じたり、一部しか観測できなかったりします。つまり、「観測したいものがそのまま得られない」という状況が日常的に起こるんです。これはCTやMRI、顕微鏡といった計測機器でも同じです。どんな装置でも、ノイズや外乱、劣化といった要素は避けられません。そうした“不完全な計測データ”から本来の情報を復元・再構成する際に、数理最適化が非常に強力なツールになるわけです。
―数理最適化は様々な分野やドメインに応用できるとわかりました。その中でも現在注力されている領域はあるでしょうか。
私の研究室では、数理最適化の考え方をベースに、さまざまな計測データの解析を行っています。その中でも今、特に力を入れているテーマが二つあります。
一つは、先ほども少し触れたリモートセンシング分野です。中でも「衛星ハイパースペクトル(HS)イメージング」という技術に注目しています。ハイパースペクトル画像というのは、数百もの波長帯で対象を分光計測したもので、人間の目では見えない物質の違いや環境変化を“色の情報”として可視化できます。環境モニタリングやスマート農業など、さまざまな社会課題の解決に活用できる一方で、観測データにはノイズや欠損が多く、解析そのものが非常に難しいという課題もあります。
そこで私たちは、ハイパースペクトル画像が本来持っている構造や計測由来のノイズの特徴を数理的にモデル化し、それを最適化の枠組みに組み込むことで、より高精度なデータ復元や解析を実現してきました。具体的には、画像に現れる縞状ノイズを除去したり、異なる解像度の観測データを統合して高精細な画像を再構成したり、長期間の衛星観測データを安定的に解析する手法を開発しています。これによって、これまで難しかった“高精細で信頼性の高い衛星データ解析”が少しずつ実現できるようになってきました。
もう一つのテーマは、日本学術振興会の「学術変革領域研究(A)」として今年度から始まったマルチスケール・ミューオンイメージング(MSMI)というプロジェクトです。これは、宇宙から降り注ぐ素粒子「ミューオン」を利用して、原子スケールから地球スケールまで、あらゆる構造を可視化しようという壮大な挑戦です。ミューオンは物質を透過する力が非常に強く、X線や電子線では見えない内部構造を観測できるのが特徴です。そのため、ピラミッド内部の構造解析のような文化財調査から、ダムや堤防といったインフラの健全性評価、地殻や火山活動のモニタリング、さらには加速器実験や原子核反応の観測まで、応用範囲が非常に広いんです。
私たちはその中で、ミューオン観測データの解析と可視化を支える数理的基盤の研究開発を担当しています。ミューオン観測では、得られるデータが非常にノイジーで、観測点も限られています。「限られたデータから内部構造をどこまで正確に推定できるか」というのが常に大きなテーマです。そこで数理最適化を活用し、ノイズに強く、信頼性の高い再構成を行うアルゴリズムを開発しています。また、ミクロな加速器実験とマクロな地球観測のように、異なるスケールのデータを統合的に扱うための枠組みも探っています。
このプロジェクトの面白いところは、物理・材料・土木・地球科学といった多様な分野の研究者が、それぞれの言葉を持ち寄って新しい“イメージングの科学”をつくっているところです。その中で数理最適化は、これらの異なるスケールや現象を結びつける“共通言語”のような役割を果たすことも期待されています。まさに「数理で現実をつなぐ」取り組みの最前線に立っている、という感覚がありますね。
数理最適化とディープラーニング──“適材適所”で使い分ける
―数理最適化はディープラーニングを補完する関係にあるとも言われますが、この二つの関係をどのようにお考えですか。
数理最適化とディープラーニングは、しばしば比較されますが、私は対立するものではなく「適材適所の関係」だと思っています。
皆さんもChatGPTのようなAIを使う機会が増えていると思いますが、ディープラーニングの中心にあるのは巨大なニューラルネットワークです。その学習には基本的に大量かつ高品質な学習データ──つまり入力に対して正しい出力がわかっているデータ──が必要になります。一方で、私たちが扱う計測データの多くはノイズが多く、欠損もあります。そもそも「正解」が存在しない場合も少なくありません。観測したい現象がすでに分かっていれば、そもそも計測する必要がないわけですから。そういう意味で、データが限られていたり、不完全だったりする状況では、ディープラーニングをそのまま使うのは難しいんです。
また、画像生成AIのように、“見た目として自然で、人がそれっぽいと感じる結果”が良しとされる分野もあります。言い換えれば、「科学的に正しい」よりも「違和感がない」「人が納得できるように見える」ことが重要な領域ですね。そうした場面では、ディープラーニングの曖昧さやブラックボックス性もある程度は受け入れられます。
でも、私たちが取り組むリモートセンシングやミューオンイメージングのような領域では、それとは少し事情が違います。見た目がきれいに再構成できればいい、というわけではなく、結果に根拠があり、再現性をもって説明できることが何よりも大切なんです。たとえば医療画像を考えてみてください。もし粗い画像をAIで補完した結果、腫瘍のように見える部分が実際にはAIが“描いてしまったもの”だったとしたら、これは大問題です。そうしたリスクを防ぐための説明性や保証を、ディープラーニング単体で確保するのは現時点では非常に難しい。
その点、数理最適化はもともと「制約条件のもとで最適な解を導く」ことを目的とする理論体系です。得られる結果には数学的な保証があり、“外部データに引きずられてそれっぽい答えを出す”ことはありません。そして何より、「なぜその結果になったのか」を理論的に説明できる。この説明可能性と保証の部分が、ディープラーニングと大きく違うところだと思います。
深い専門×広い知識──独創性は“組み合わせ”から生まれる
―研究で成果を出していくために、小野先生が意識されていることは何でしょうか。
まず一番大事なのは、当たり前のことかもしれませんが、自分の専門性をしっかり掘り下げることだと思います。これは自分自身への戒めでもあるんですが、流行している技術に次々と飛びついて、そのときどきで論文を書いて終わってしまうようなやり方は、あまり長続きしません。そうしているうちに、「自分の専門的な軸は何なのか」が分からなくなってしまうんです。
技術の流行は時代とともに変わります。でも、普遍的な専門性を一つ軸として持っていれば、「自分が本当に取り組むべき研究」や「自分にしかできない研究」が自然と見えてきます。流行を追うのは最初のうちは刺激になりますが、やがて競争が激しくなり、「自分でなくてもいい研究」になってしまう。たとえニッチな領域であっても、「自分がやらなければ誰もやらない」と思えるテーマを見つけることが、やはり大切だと感じています。
それから、アイデアというのはゼロから生まれるものではないとも思っています。過去の偉人も似たようなことを言っていますが、そのほとんどは、既存の知識や発想の組み合わせによって生まれるものです。特に、一見すると関係のないものを結びつけられたときほど、研究としての独創性が評価される。だからこそ、一つの専門を深めるのに加えて、周辺分野の幅広い知識を持つことも欠かせません。しかもその知識は、特定の分野や時代に偏らないほうがいい。いろんな視点を持っていれば、それだけ思いもよらない組み合わせが生まれるんです。
そして、そうした異なる知識をつなぐための“共通の言語”として、数学はとても有効だと感じています。数学は情報系分野に限らず、全く異なる分野の間に潜む共通構造を見いだすための強力なツールなんです。構造が見えれば、異分野のアイデアを自然に組み合わせて、新しい発想につなげることができる。こうした“橋渡しの感覚”こそが、私にとって数学の一番の魅力ですね。
―自分の専門性を見つけて取り組んだとしても、研究の方向性が違ったと感じることはあると思います。学生の研究テーマを決めるときなどは、どのように判断や方向転換をされていますか。
研究テーマを決める際には、私が一方的に指示するのではなく、学生と一緒に考えるプロセスを大切にしています。まず私が、研究テーマの候補となりそうな論文を毎年100本以上リストアップし、その中から学生自身に興味のあるものを選んでもらいます。選んだ論文を読み込み、発表してもらう中で、最終的なテーマを一緒に絞り込んでいくという方法を取っています。
このやり方を始めてから、テーマを決めた後にしばらく経って「やっぱりこのテーマは違ったね」となるようなことはほとんどなくなりました。というのも、最初の段階で「この方向性は面白くない」「研究室の強みと相性が悪い」「既に競争が激しい」「類似研究がすぐ出てしまいそう」といったテーマを事前に除外しているからです。
私自身、見た目は格好良くても、実際の現象や課題とまったく結びつかない研究にはあまり惹かれません。もちろん、理論を磨くこと自体にも大きな価値がありますが、私はその理論が現実のデータや問題に触れたときにこそ、本当の面白さや手応えを感じます。だからこそ、研究室で進めるテーマについても、理論やアルゴリズムを作って終わりではなく、必ず実際のデータ解析に適用し、その有効性を確かめるところまでを一連の流れとして大切にしています。
―土台固めと学生の自主性を尊重する素敵なテーマ選択のプロセスですね。研究を進める上では先生の「哲学」や軸としている考え方はありますか。例えば、「役に立つ研究」と「面白いと思う研究」のどちらを取るかという二項対立があったりします。
そうですね。どちらかというと私は、「世界の真理を突き止めたい」といった強い使命感を持って研究しているタイプではありません。それよりも、自分や周りの仲間が楽しく日々を過ごしながら、その活動を通して少しでも人や社会に良い影響を与えられたらいいな、というくらいの気持ちでやっています。そういう意味で、研究という仕事は自分に合っていると感じています。特に情報系の研究は、社会との距離が近く、成果が実世界に還元される実感が得やすいところが魅力ですね。
私にとって研究の面白さは、テーマの“内容”だけではなく、その“進め方”や“過程”にもあると思っています。たとえば、地道な実装や検証の積み重ねの中に手応えを感じる人もいれば、発表や論文執筆を通して自分の考えを形にすることに喜びを見いだす人もいる。どの部分に面白さを感じるかは人それぞれで、研究という営み自体が多様な魅力を持っていると思うんです。
ですから私は、「役に立つ研究」と「面白い研究」を対立するものとしては考えていません。社会に貢献できることに面白さを感じる人もいれば、自分の純粋な好奇心を突き詰めることに価値を感じる人もいる。どちらの方向にも意味があって、研究の世界はその両方があるからこそ豊かになる。私自身も、その間のどこかでバランスを取りながら日々研究している感覚です。
刀は切れる、でも豆腐を切っていた──転機から見えた道
―研究者として困難に直面し、それを乗り越えた経験があれば教えてください。
研究が思うように進まず、「このまま研究者を続けていけるのか」と悩んだことはありませんが、一時期、研究に対するモチベーションを失ってしまったことがありました。博士課程の頃はどちらかというと理論寄りの研究に没頭し、運よく権威ある国際誌に論文を掲載することができました。けれども、次第に違和感が生まれたんです。理論としては洗練されていても、現実の問題解決にはあまり結びついていない。「よく切れる刀を作ったのに、切っているのは豆腐だった」という感覚でした。トップジャーナルに通すための“型”のようなものも見えてきて、研究そのものを作業のように感じるようになってしまった。あえて乱暴な言い方をすれば、研究者という“ゲーム”に少し飽きてしまった時期がありました。
転機となったのは、2016年にJSTさきがけ「情報計測」領域に研究提案が採択されたことです。そこでは、情報系“以外”の様々な分野の研究者が抱える計測の課題を情報技術で解決するというテーマに取り組みました。自分の理論的な最適化技術が、他分野の実問題の解決に直接役立つ場面を目の当たりにして、「こういうところにも使えるのか」と強く感じたんです。これが、現在の研究スタイルの原点になりました。ただ、それでも、すぐに「研究をやりたい」という気持ちが戻ったわけではありません。
もう一つの大きな転機は、研究室を持ち、学生と一緒に研究を進めるようになったことです。学生が成長していく姿を見たり、研究室という組織をどう育てていくかを考えたりすることが、次第に自分にとっての大きな楽しみになっていきました。今では、「自分がすごい論文を一本書く」ことよりも、「研究室全体で人が育ち、成果が積み上がっていくこと」にこそ価値を感じています。研究室を一つのチームとしてどう導いていくかを考えることで、若い頃に感じていた閉塞感が自然と解けていきました。個人としての成果よりも、人と組織を通して研究が広がっていく面白さ──それが、いまの自分を支える原動力になっています。
― 様々な異分野連携を進めているかと思いますが、共同研究を進めていく上で気をつけていることや重要にしているポイントはありますか。
まず一番大切なのは、お互いにとって気持ちのいい関係であること、つまりWin-Winであることだと思っています。情報系の研究者なら共感してもらえると思いますが、「情報技術を使いたいから教えてほしい」という形で声をかけていただく共同研究は本当に多いんです。もちろん、それ自体はすごく大事なことですし、相手の課題を技術的に支援するのも研究者の役割の一つです。ただ、それだけで終わってしまうと、こちらとしては新しい学術的な意義や発展の方向を見いだしにくくなってしまいます。いくら研究費をいただいたとしても、情報技術としての新しい発見や理論的な貢献につながらない共同研究は、結局どちらにとっても長期的なプラスにはならないんですよね。
ですから、できるだけ対等な立場で学び合える関係を築くようにしています。たとえば、相手の分野特有の課題から「こういう最適化技術が必要だ」という具体的な要望が生まれたとします。そうすると、それを解決する過程で、こちらも新しい数理最適化の理論や手法を開発できる。こういう形が理想的だと思っています。相手の分野にも貢献できて、情報系としても新しい知見を得られる──そうした関係が一番健全で楽しいですね。
もう一つ大事にしているのは、前提知識と共通言語のすり合わせです。特に異分野の研究では、いきなり専門的な話をしてもなかなか通じません。使っている言葉の意味が違っていたり、背景の知識がずれていたりすることが本当によくあります。ですから最初の段階では、お互いの前提を丁寧に共有することを何より重視しています。一見すると時間がかかるように見えますが、実はこのステップが後の研究をスムーズにする“要”なんです。
それともう一つ、研究とは直接関係ないような雑談も大切にしています。仕事以外の話をしたり、ちょっとしたプライベートな会話をしたりすることで、人間関係の壁がぐっと低くなるんですよね。そうして気軽に話せる雰囲気ができると、「あのとき聞けばよかった」「言いにくくて伝えられなかった」ということが減ります。当たり前かもしれませんが、結局のところ、いい共同研究は人と人との信頼関係から生まれるものだと思っています。
研究を動かす“人と場”──博士号が拓く力、空間が育む意欲
―研究室の公式サイトに「情報系博士号は強い味方である」と書かれていました。その理由を詳しくお聞かせください。
「情報系の博士号は強い味方だ」と思う理由はいくつかあります。
まずはやはり、情報技術のニーズの高さですね。今の社会では、最先端の情報技術を扱える人材が圧倒的に足りていませんし、この流れはしばらく変わらないと思います。情報技術が社会の根幹を支えるようになって久しいですから、情報系の博士を持っているということは、それだけで安定したキャリアの土台になる。そういう意味で、とても心強い資格だと思います。
もう一つは、最近の研究と社会の距離がすごく近くなっていることです。論文で発表された技術が、数カ月後に実用化されるような時代です。そうした技術を理解し、実際に実装や改良まで手を動かせる人は産業界でも非常に重宝されます。情報系の博士は、まさにその橋渡し役になれる存在だと思います。
それから、これは情報系に限らず博士課程全般に言えることですが、博士号の価値は「問題解決の型を身につけられること」だと感じています。つまり、ある分野の専門的な考え方やアプローチを自分の中に根づかせて、他の分野にも応用できるようになる。そういう人がいろんな分野から集まることで、これまでの発想では解けなかった社会の課題にも新しい視点で取り組めるようになるわけです。
そして最後に、もうひとつ大事なのが「問題を見つける力」です。研究というのは、与えられた課題をこなすことではなく、「何が本当の問題なのか」「まだ誰も気づいていない課題は何か」を見抜くところから始まります。その力こそが博士課程で一番鍛えられる部分であり、どんな分野でも強みとして生きると思っています。
―カフェのような研究環境を整えられているとお聞きしましたが、その理由をお聞かせください。
もともと私自身、オフィスのように硬い雰囲気の場所があまり得意ではなくて(笑)。できればもう少しカジュアルで、ふらっと立ち寄りたくなるような研究室にしたいなと思っていました。
「学生が研究室に来ない」という話題は、大学教員の間でよく出るんですが、私は“来ないこと”そのものを問題視する前に、「来たくなる研究室になっているか」を考えることの方が大切だと思っているんです。コアタイムなどを決めて強制的に集めるのではなく、「今日はちょっと時間があるからラボに行ってみようかな」と自然に思えるような場所にしたくて。
そんな思いから、研究室の空間づくりにもかなりこだわりました。天井を抜いて開放感を出したり、間接照明を入れて柔らかい光にしたり、コーヒーマシンを置いたりして、カフェのように居心地のいい雰囲気にしています。私自身も、休日にふらっと立ち寄ってコーヒーを片手に仕事をすることが多いですね。研究室というより、リビングルームに近い空間かもしれません。
―お話の中で学生の主体性を重視されていると感じました。その中でもどかしさを感じることはありますか。
研究室を運営していていつも感じるのは、自分ではコントロールできないことの方が圧倒的に多いということです。よく「馬を水飲み場に連れていくことはできても、水を飲むかどうかは馬次第」と言いますが、本当にその通りだなと思います。学生も同じで、無理に動かすことはできませんし、そうするべきでもないと思っています。研究室における教育というのは、こちらの思い通りにいくものではないんですよね。
だからこそ、私が意識しているのは、自分が手を入れられる部分に注力することです。たとえば、快適な研究環境をつくることや、学生が自然にやる気を出せるような仕掛けを用意すること。あとはもう、どんなふうに動くかは学生に任せています。結果まで全部コントロールしようとすると、お互いに苦しくなりますからね。ある程度は「うまくいかないこともある」と受け止めて、見守るようにしています。
それから、大学教員ってつい「研究は面白いもの」という前提で話をしてしまいがちなんですが、学生にとっては必ずしもそうではないんです。彼らには研究以外にも、興味のあることや優先したいことがたくさんあります。私もゲームやアイドルが大好きなのでよくわかります(笑)。だから、「学生は必ずしも研究ファーストではない」という前提を持つことは、教員にとってすごく大切だと思っています。
カフェのように居心地の良い空間を整えても、来ない学生はやっぱり来ません。でもそれでいいと思っています。大事なのは、学生の主体性を尊重して、学びの環境とチャンスをきちんと用意しておくこと。そのうえでどう行動するかは学生次第ですし、結果がどうであってもそれを受け止める──そういう姿勢が、長く続く研究室運営には欠かせないと感じています。
キャリアは“待つ”ものではなく“築く”もの──発信と選択の主体性
―アカデミアの世界でキャリアを築き続けるうえで、特に意識されてきたことはありますか。
アカデミアの世界では、自分から発信しなければ誰にも気づかれないという現実があります。「いい研究をしていれば、いずれ誰かが見つけてくれるだろう」という考え方もありますが、今の時代、それだけではなかなか難しいと思っています。フィールズ賞を取るような天才的な研究者なら別かもしれませんが、私を含め多くの研究者はそうではありません。だからこそ、自分が何を得意としていて、どんな研究をしているのかを、積極的に外へ伝えていくことが大事だと思っています。自分では「ちょっと地味かな」「大したことないかも」と感じる研究でも、他の分野の人にとってはとても価値のある成果だったりするんですよね。どんな研究でも、きちんと論文として形に残すこと。それが一番基本的で、かつ確実な発信の方法だと思います。
競争的資金への応募も同じです。もちろん、採択されるかどうかには運の要素もあります。でも、それ以上に大事なのは、自分の研究を社会や資金提供側に知ってもらうこと自体に意味があるということです。「どうせ通らないだろう」「今回はやめておこう」と考えるより、とにかくまず出してみる。実際、応募をきっかけに新しいつながりや機会が生まれることも少なくありません。
―若手研究者はラボ選びに悩んでいることが多いと聞きます。どのラボ出身かということも気にした方が良いとお考えですか。
難しい質問ですが、個人的には「どのラボ出身か」を見られる場面は確かにあるものの、それがすべてではないと思っています。分野の特性や、自分がどんな研究者を目指したいかによって、見るべきポイントは変わってくるので。
たとえば自然科学系の中には、大規模な装置や長年のチーム体制が前提になっている領域もあります。そういう分野では、伝統ある大きなラボに入ること自体に大きな意味があるでしょう。一方で、情報系は少し違うと思っています。個人や小規模チームでも、工夫次第で成果を出せるテーマが多い。ですから、「有名なラボに入らなければダメだ」という必然性は、相対的に小さいと感じています。
ただし、“看板が要らない”という意味ではありません。たとえば、特定の装置やデータ、共同ネットワークがないと成り立たないテーマもありますし、競争的資金への応募などの場面では、ラボの実績やチーム体制が重視されることもあります。ですから大切なのは、「どこに所属するか」よりも「その環境で自分が何をできるか」という視点だと思います。
私自身の考えでは、ラボ選びには“看板”と“中身”の両方があります。“看板”は、その分野での研究実績や外部資金の獲得状況など、外から見える部分。一方で“中身”は、教員との相性、研究の自由度、サポート体制など、実際に入ってみないと分からない部分です。学生の皆さんには、どちらか一方に偏らず、両面をしっかり見てほしいと思っています。情報を集めるときは、たとえばGoogle Scholarで教員の論文や引用数を見たり、研究室のWebサイトでテーマや外部資金、共同研究の様子をチェックしたりするのも良いでしょう。博士課程の学生がどのくらいいて、どんな進路を歩んでいるかを見るのも参考になります。
でも、やっぱり一番大事なのは、実際にそのラボを訪れて、教員や学生と話してみることですね。研究の雰囲気や日々のやり取り、指導のスタイルなど、数字や実績では見えない部分がたくさんあります。結局のところ、ラボ選びは「どこが有名か」よりも、「自分が納得して研究に打ち込めるか」です。自分のやりたいことやスタイルと合う環境を見つけることが、長く研究を続けるうえで一番の近道だと思います。
株式会社CoA Nexus編集部 コメント
小野先生のインタビューを通じて、数理最適化という理論的基盤が、分野を超えて現実世界の複雑な課題解決に応用されていることを改めて実感しました。ノイズや不完全なデータの中から信頼性ある情報を導き出すという研究の姿勢は、AIやディープラーニングが直面する「説明性」や「再現性」といった課題にも通じる重要な視点です。
また、異分野の研究者との協働を通じて新たな知を創出し、学術的な成果を社会に還元していく取り組みは、私たちが掲げる「研究革命で豊かな未来を」というビジョンとも深く響き合います。CoA Nexusは今後も産業の境界を越えた連携を支援し、研究の可能性を社会の力へと変える循環づくりに挑戦していきます。
最後に、よろしければ、本インタビューのご感想をお聞かせいただけますと幸いです。